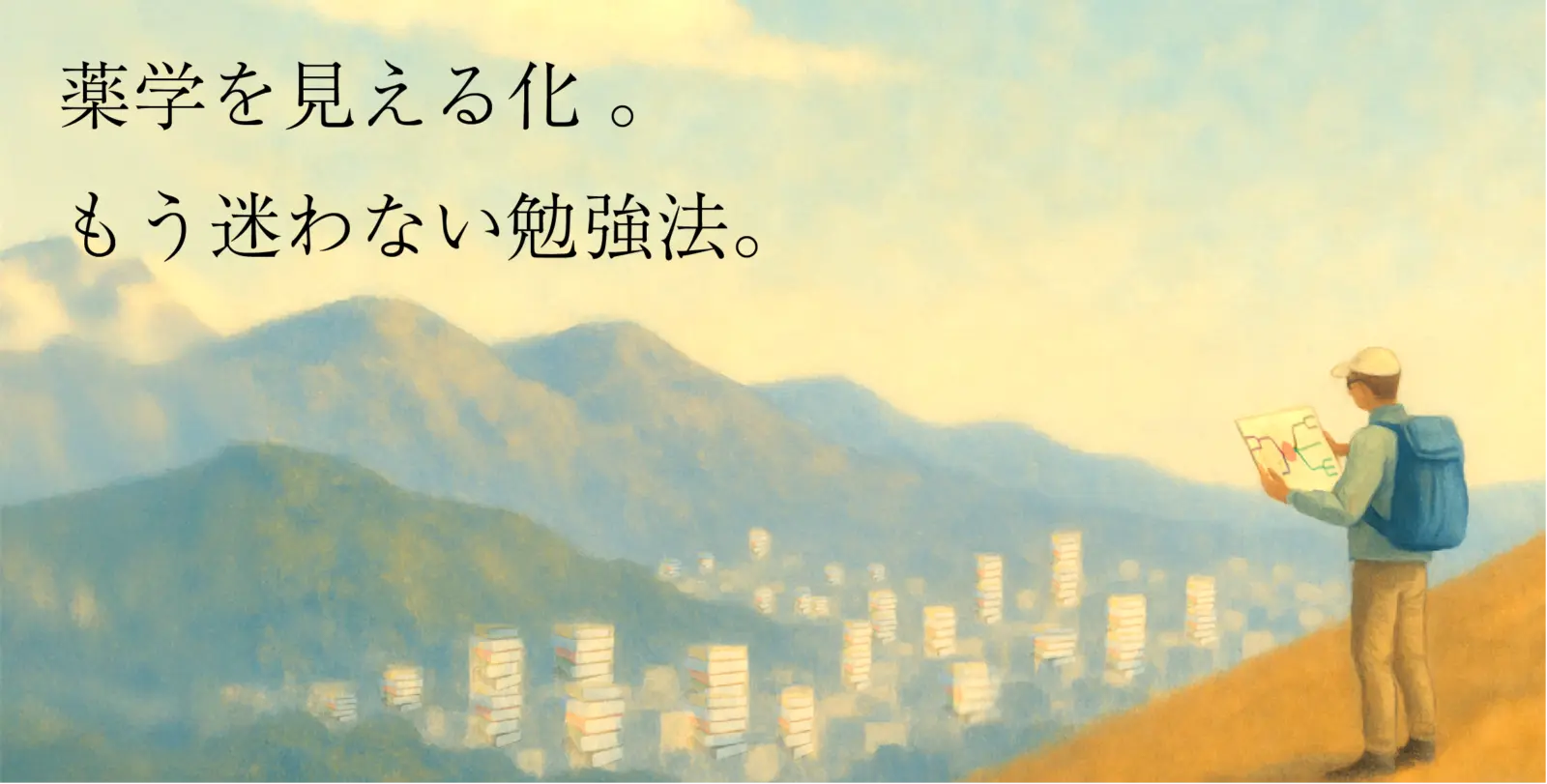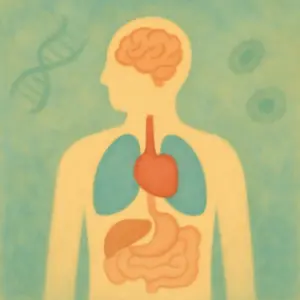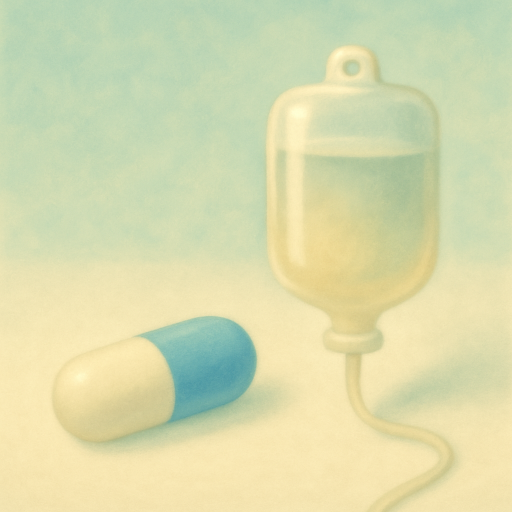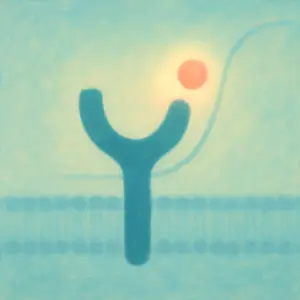マインドマップの3つの強み
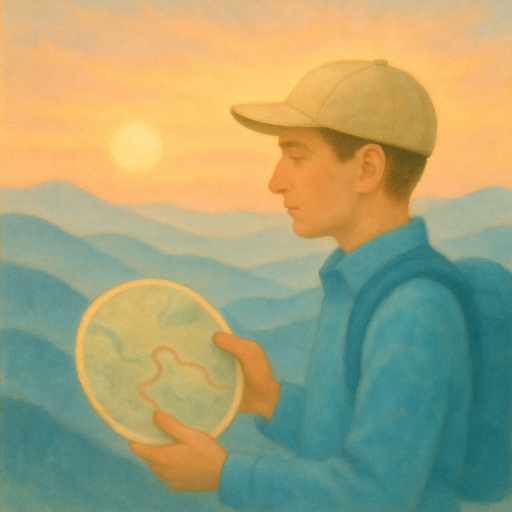
全体像が一目でわかる
勉強範囲の有限化
《おすすめの記事》

芋づる式に思い出せる
《おすすめの記事》
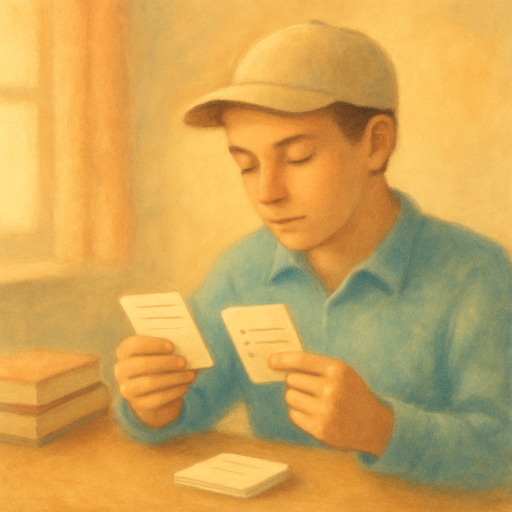
覚える範囲がわかる
ゴロも入ってる
こんな人におすすめ
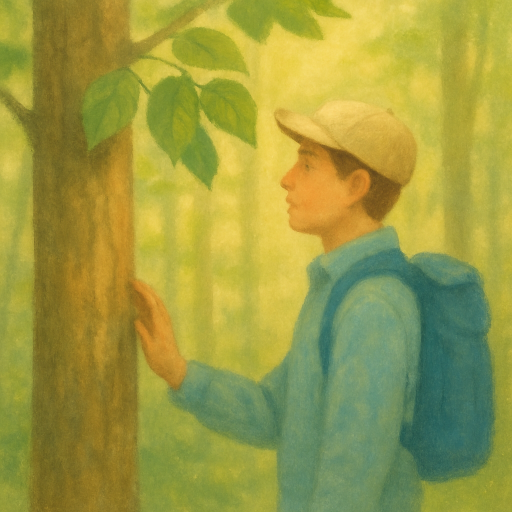
部分に捉われて進まない
調べ始めると深みにハマる
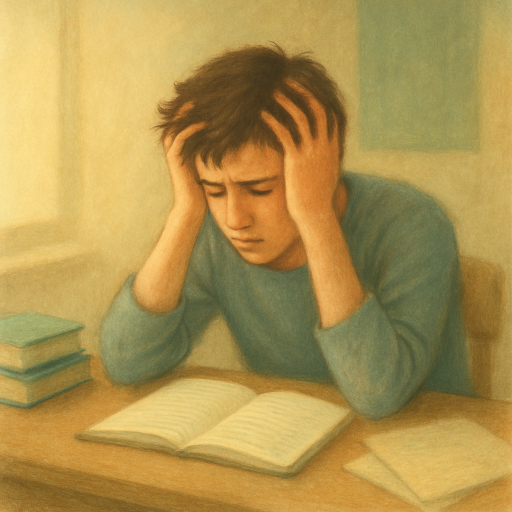
関連付けて覚えるのが苦手
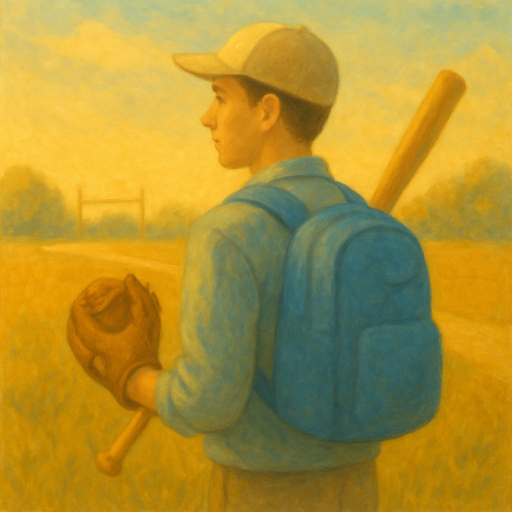
不安で勉強範囲を広げてしまう
対象別の勉強法
薬学部6年生
最短で終わらせる
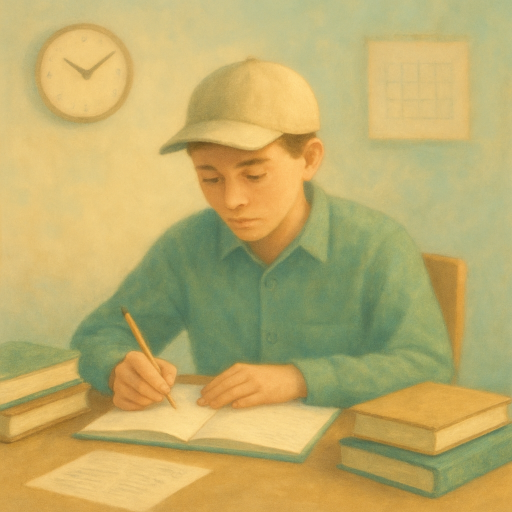
- 理解
マインドマップ見ながら授業やテキストで勉強 - マインドマップを暗記
見ないで言えるかチェック - 繰り返し暗記
卒試前、国試前に暗記
薬学部1〜5年生
学校の授業に活用
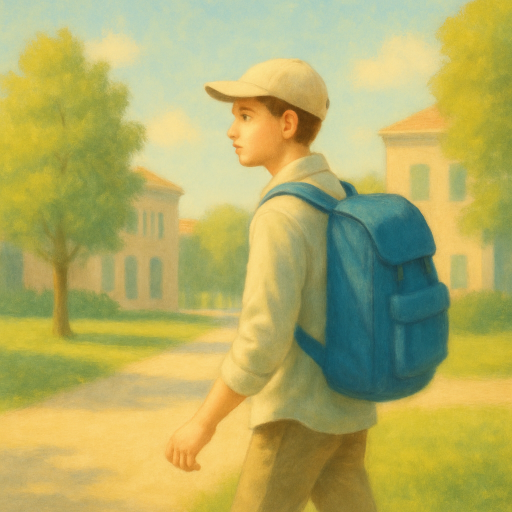
- 授業の理解が上がる
- 学校の授業が体系化され蓄積
- 6年次は復習するだけ
実習生、社会人1年生
出会った薬を確認
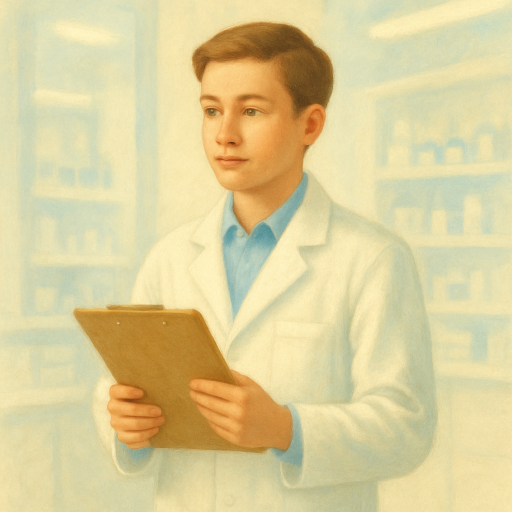
- 実習や仕事で触れた薬を病態薬理のマインドマップで確認
- 一般名→商品名を書き込む
- 同系統の薬の違いも付け足す
科目
化学、物理、実務のPDFは準備中です。
Q & A
Q1.マインドマップで本当に覚えられますか?自分で書けなくても使えますか?
A1. 圧倒的に効率よく覚えられます。
→記事「暗記の仕方」
内容を理解した後、
「①全体像を見る → ②ゴロを暗記 → ③空白再生(見ずに思い出す)」
の3ステップ。
自作は必須ではありません。用意したマップを“辿る→思い出す”反復で効果が出る設計です
Q2. どの科目・どんな順番で進めるのが良いですか?
A2. 病態薬理から始めるのがおすすめです。
→記事「最初の1科目目」
6年生なら、病態薬理から始めて、全科目をまず理解。
その後、1周目の暗記期間に入ります。(1科目2〜3日)
Q3. 端末や運用はどうすれば?印刷は可能ですか?
A3.推奨はタブレットまたはA3印刷です。PC・スマホでも利用可能。
PDFに書き込めます。印刷は個人利用の範囲でOKです。
制作の背景/講師紹介
学生のころに出会ったマインドマップが、勉強を「見える化」してくれました。
授業内容を整理しながら理解することで、時間と心の余裕が生まれました。
そして学生時代、勉強だけでなく、興味のあるさまざまなことに挑戦できるようになりました。
そんな体験を、同じように頑張る人たちにも感じてもらいたく、この教材を作っています。
講師紹介
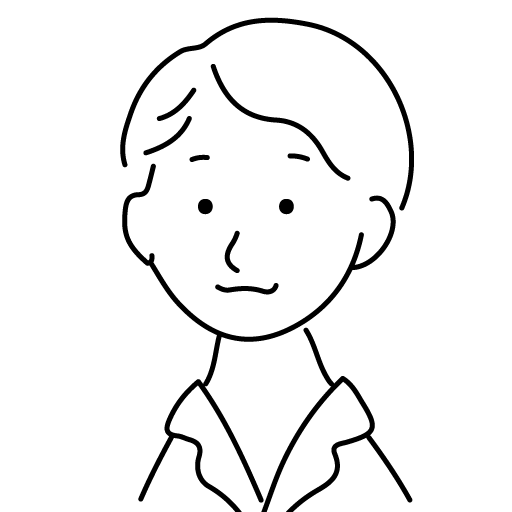
講師:トンキチ
調剤薬局で薬剤師を経験。その後、美術大学で建築とアートを学び、大工としてものづくりの現場にも携わってきました。
異なる分野を横断して学ぶ中で見えてきた「理解の構造」を、学びに活かす形として「マインドマップ薬学」を制作しています。
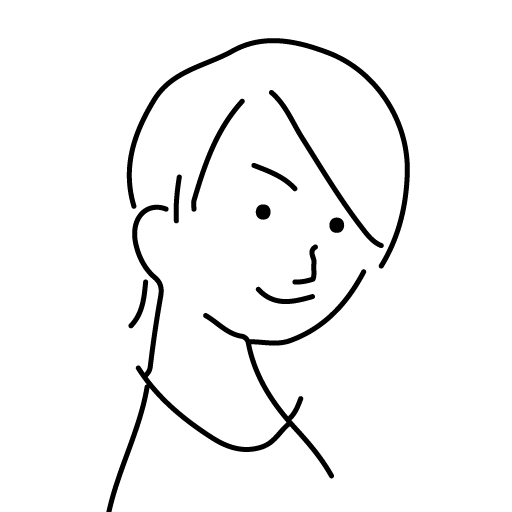
講師:タラコ
大学では医療統計を専門に研究。
その後、病院と薬局の両方で経験を重ね、臨床現場の視点を培いました。
現場で求められる知識のつながりや理解の深さを、マインドマップという形で体系化しています。
各教科の商品説明欄にサンプルを置いています。
ぜひ手に取ってみてください。